Photography
「神の宮」伊勢神宮 第62回式年遷宮
2013年10月、伊勢神宮の内宮と外宮では、ご正殿のご神体をお遷しする“遷御の儀”が執り行われました。内宮の正式名は皇大神宮、ご祭神は天照大御神です。皇室の御祖神であり、私達の総氏神でもあられます。一方、外宮の正式名は、豊受大神宮、ご祭神は、豊受大御神です。神々に奉る食物を司られており、衣食住から広く産業の守護神として崇められています。
伊勢神宮では20年に一度式年遷宮が行われ、内宮・外宮のご正殿をはじめ神苑内の社殿や鳥居を新築し、宇治橋を架け替えます。また御神宝や御装束も新調して常若の世を願います。遷宮の周期を20年とすることで、日本の粋を極めた伝統的な技術も代々受け継がれて行きます。この繰り返しが凡そ1300年続いて来ました。定期的に再生することで永遠を保つ遷宮の思想とシステムは正に持続可能な世界に通ずる文化です。
森羅万象に魂が宿る=八百万の神という日本古来の思想は自然崇拝を起源とし、万物と共生共存することで命が永遠に受け継がれて行くことを願っています。その願いは遷宮にも受け継がれています。イギリスの偉大な歴史哲学者であるアーノルド・コ・トインビーは1967年に伊勢神宮を訪れた際「この聖なる地で、私はすべての宗教に通底する一なるものを感じる」と記しました。
どの国、どの地域にも、それらの風土に根付いた文化があります。一方の物差しで判断するのではなく、互いが理解に努め尊重することで無残な争いは無くなるのではないかと考えます。また、近代科学文明が発達するまでは、日本古来の精神文化とも通底するアニミズムが世界各地に存在していました。原始宗教として遠ざけるのではなく、地球とそこに宿るあらゆる生命体のためにも、改めてその本質を見直し、未来へと受け継がれることを願います。
-

宇治橋 
宇治橋
清流 五十鈴川に掛かる橋。宇治橋は、俗界と聖界の境にあると言われ、参拝者はこの橋を渡って神苑に入る。水晶のように澄んだ川のせせらぎを渡りながら、心まで洗われて行くのを感じる。
-

古殿地【内宮】 
古殿地【内宮】
「神の宮」の始まりの一枚。神苑の中に、冬の柔らかな日射しを浴びて一際輝く場所があった。それが今回の遷宮で新宮(にいみや)が建てられる土地だ。鎮地祭(ちんちさい)迄は古殿地と呼ばれるが、それ以降は、新御敷地(しんみしきち)となる。伊勢神宮では御正宮の隣に御敷地を設け、新しい御正宮を建てる。二つの土地が交互に古殿地となり御敷地となる、その繰り返しが1300年続いて来た。
-

鎮地祭参進【内宮】
平成20年4月25日
鎮地祭参進【内宮】
平成20年4月25日鎮地祭にお仕えする為に斎場に向う神職達。鎮地祭は、新宮(にいみや)を建てる御敷地(みしきち)で行われる最初の祭儀。一般の地鎮祭にあたるが、斎行の日時は天皇陛下がお決めになる重要な祭典の一つ。新宮造営の前に大宮地(おおみやどころ)に坐す神を鎮めまつり、御敷地の平安と造営の安全を祈願する。
-

鎮地祭 二【内宮】
平成20年4月25日
鎮地祭 二【内宮】
平成20年4月25日鎮地祭に奉仕する神職。二人の所作がまるで舞っているように見える。
-

鎮地祭 二【外宮】
平成20年4月25日
鎮地祭 二【外宮】
平成20年4月25日祭典の前に、奉仕する神職達をお祓いする。神職達は、心身共に清まった状態で祭事に臨む。身の回りを清潔に保つ日本人の習性は、神事に由来していると考えられる。
-

宇治橋渡始式
平成21年11月3日
宇治橋渡始式
平成21年11月3日20年の間に延べ一億人もの参拝者が宇治橋を渡る。宇治橋渡始式とは、橋の竣工を祝い、その安全を祈念する式典。宇治橋の守護神をお祀りする饗土橋姫神社(あえどばしひめじんじゃ)での祭典の後、伊勢市内から選ばれた渡女(わたりめ)ら三夫婦を先頭に、一同揃って渡始を奉仕する。渡女の長寿と三代の夫婦の和合にあやかり、橋の永遠と安全を願うためと考えられている。
-

上棟祭退下【内宮】
平成24年3月26日
上棟祭退下【内宮】
平成24年3月26日上棟祭とは、新しい御正殿の棟木を掲げる際に執り行われるお祭。先ず御正殿の位置が古規(こき)に違わないか丈量(じょうりょう)の儀を行い、続いて、大宮司以下神職並びに造営庁職員一同が引綱に手を掛け棟木を掲げまつる。ここでも大宮地(おおみやどころ)に坐す屋船大神(ヤフネノオオカミ)に神饌を供え、祝詞を奏上してお祀りする。
内宮の上棟祭が終わり神職達が退下している。神事では、退出のことを退下、神前や祭儀に向かって進むことを参進と言う。 -

五十鈴川 御手洗場【内宮】 
五十鈴川 御手洗場【内宮】
内宮を流れる五十鈴川は、一夜の雨で濁ってもすぐにもとの清流に戻る。まず、五十鈴川で手を清め、心も澄ませてからお参りするのが、いにしえより伝わる本来の作法である。
-

新宮 一【外宮】
平成25年9月4日
新宮 一【外宮】
平成25年9月4日外宮の新宮。10月5日の遷御で、御祭神である豊受大御神(トヨウケノオオミカミ)が遷って来られる。本来、入ることはおろか見ることも許されない神域。真新しい檜の清々しい香りが辺りを満たし、崇敬者達によって敷き詰められた白石も眩く、新宮は光を放つように神々しく輝いている。
新宮は日本古来の建築様式を伝え、檜の素木(しらき)を用い、高床式の穀倉の形から宮殿形式に発展した。穀倉の形がご正殿に反映されているのは、それほどお米が貴重なものであったということだ。 -

新宮 三【外宮】
平成25年9月4日
新宮 三【外宮】
平成25年9月4日外宮の新宮。10月5日の遷御で、御祭神である豊受大御神(トヨウケノオオミカミ)が遷って来られる。本来、入ることはおろか見ることも許されない神域。日本古来の建築様式を伝え、檜の素木(しらき)を用い、高床式の穀倉の形から宮殿形式に発展した。穀倉の形が御正殿に反映されているのは、それほどお米が貴重なものであったということだ。
-

新宮 六【外宮】
平成25年9月4日
新宮 六【外宮】
平成25年9月4日外宮 新宮の側面。太い棟持柱が両妻を支えている。撮影当日、伊勢の天気は荒れ模様だったが、雲の合間から新宮に光が射した。御正殿の床下には“心御柱(しんのみはしら)”が建てられており、そこに神が宿ると言われている。
-

新宮 一【内宮】
平成25年9月4日
新宮 一【内宮】
平成25年9月4日内宮では、10月2日に御祭神の天照大御神(アマテラスオオミカミ)が新宮に遷られる。
新宮は、唯一神明造(ゆいいつしんめいづくり)と言う日本古来の建築様式によって建てられている。20年に一度、神苑内の全ての御社殿や鳥居を新築し、宇治橋まで架け替える遷宮には、膨大な御用材が必要である。その為、伊勢神宮では、大正時代から200年後の遷宮を想定して檜を育成している。また、旧社殿の廃材は、全国の神社の修繕や災害に遭った神社の再建等に使用される。どの古材も元は自然からの授かりものであり、決して無駄にされることはない。遷宮を通して自然と共に生きる心、ものを大切にする心が受け継がれている。 -

新宮 三【内宮】
平成25年9月4日
新宮 三【内宮】
平成25年9月4日新宮の高欄には美しい細工が施されており、細部に至るまで、伝統に支えられた職人の技が光っている。
御垣の向こうに見えるのは当時の御正宮。伊勢神宮では御正宮の隣に御敷地(みしきち)を設け、新しい御正宮となる新宮を建てる。二つの土地が交互に古殿地(こでんち)となり御敷地となる。その繰り返しが1300年も続いて来た。新宮が完成し、遷御でご神体が遷られたしばらくの間、空からは同じ建物が二つ並んでみられる。世界でも類を見ない光景だろう。繰り返し行われることで、遷宮に象徴される日本の精神文化の尊さを再認識出来るのだ。 -

抜穂祭 二
平成25年9月5日
抜穂祭 二
平成25年9月5日抜穂祭とは、伊勢神宮の神田にて、今年初めての稲を刈り取る儀式。これは、伊勢神宮の重要な祭事である神嘗祭に繋がるお祭りで、実りに感謝しながら古式ゆかしく行われる。
神田は、3ヘクタールの面積があり、内宮を流れる五十鈴川から引き込んだ水をもとに、21区画で10種類の稲を栽培している。9月中には全ての稲が刈り取られ、内宮の御稲御蔵(みしねのみくら)と外宮の忌火屋殿(いみびやでん)で保管され、10月15日から行われる神嘗祭と、6月と12月の月次祭(つきなみさい)で御神前に供えられる。 -

雨儀廊【内宮】 
雨儀廊【内宮】
御正宮前から新宮(にいみや)へと続く雨儀廊は、遷御の際、御神体が雨に濡れないようにと設けられている。遷御が終わるとすぐに取り除かれるので、普段見ることは出来ない光景だ。
-

川原大祓 一【内宮】
平成25年10月1日
川原大祓 一【内宮】
平成25年10月1日翌日に遷御を控えた10月1日、内宮の川原祓所(かわらはらえしょ)では、新正宮に収める神宝類や儀式にかかわる神職などを全て祓い清める川原大祓が行われた。御装束神宝類(おんしょうぞくしんぽうるい)などは全て、素木や朱塗りの辛櫃に納められている。
内宮の御装束神宝は540点。日本の技術の粋が結集されている。20年に一度の式年遷宮で、その貴重な技術も受け継がれて行く。 -

川原大祓 二【内宮】
平成25年10月1日
川原大祓 二【内宮】
平成25年10月1日内宮の川原大祓に池田厚子祭主を始め、大宮司・少宮司以下ご奉仕する全ての神職などが集まった。神職達は皆、遷御で身につける装束を纏っている。古来の装束は着付けが非常に難しい。平安末期に威儀正しい装束として考案された剛装束(こわしょうぞく)を美しく着用する技術を“衣紋道(えもんどう)”と言い、この特別な作法が旧華族を中心とした人達によって受け継がれている。
-

遷御の儀 一【内宮】
平成25年10月2日
遷御の儀 一【内宮】
平成25年10月2日午後8時前、庭燎が全て消された浄闇の境内に「カケコウ」と三回、神職が発する鶏鳴が響く。これは天岩戸開きの故事に倣っている。鶏は、天照大御神がお隠れになった天岩戸から鳴き声で大御神を迎えだし、闇に包まれた地上から光に満ちた平和な世界を取り戻すことが出来たと伝えられている。
鶏鳴の後、勅使が階下にて「出御(しゅつぎょ)」と三度唱えられる。8時丁度に、大宮司・少宮司・禰宜に奉載された神儀(しんぎ)が純白正絹の行障(こうじょう)・絹垣(きんがい)に秘められ、厳かに御正殿から新宮へと遷られるのである。
神宮では重要な祭事は全て夜に執り行われる。参道の明かりも消し、清浄な空気に満ちた闇のことを浄闇と言う。 -

古物渡 二 【内宮】
平成25年10月3日
古物渡 二 【内宮】
平成25年10月3日ご神体が新宮(にいみや)に遷られたので、昨日迄の御正殿は、古殿(こでん)と呼ばれる。その古殿内の御神宝類を、御正殿の西宝殿(さいほうでん)に移すことを古物渡と言う。
-

御神楽 御饌【内宮】
平成25年10月3日
御神楽 御饌【内宮】
平成25年10月3日遷御の儀の翌日に初めて奉納される御神楽に先立ち、大御饌と言われる神饌を神前に奉る。祭儀の前に、忌火屋殿(いみびやでん)前で奉仕する祭員達を榊で祓い清める
-

遷御の儀 一【外宮】
平成25年10月5日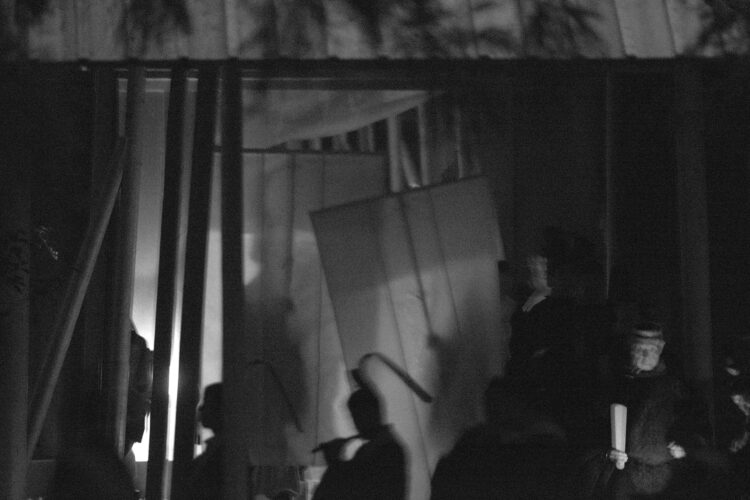
遷御の儀 一【外宮】
平成25年10月5日午後8時、内宮の「カケコー」とは違う鶏鳴「カケロー」と神職が三唱して遷御の儀が始まる。これは天岩戸開きの故事に倣っている。鶏は、天照大御神(アマテラスオオミカミ)がお隠れになった天岩戸から鳴き声で大御神を迎えだし、その再現を世に知らせた。そして、闇に包まれた地上から光に満ちた平和な世界を取り戻すことが出来たと伝えられている。
鶏鳴の後、勅使が階下にて「出御(しゅつぎょ)」と三度唱えられる。浄闇の中、絹垣(きんがい)に秘められて厳かに御神体が出御される。「おー、おー」と低く歌うような神職の声と共に、雅やかな道楽(みちがく)の音色が導いている。 -

御神楽 一【外宮】
平成25年10月6日
御神楽 一【外宮】
平成25年10月6日御神楽と秘曲(ひきょく)をご奉納する為、宮中の楽師達が天皇陛下から差し遣われた。お祝いの御神楽は深夜まで続き、この祭典を以て第62回神宮式年遷宮の主な行事は終了となる。
宵闇が迫り神苑の空気は神秘さを増して来た。千数百年に渡る悠久の時が静かに流れている。神宮ではこれからも果てしない時間を神々と共に紡ぎながら、感謝の祈りを祭事に込めて後の世に伝えて行くのだ。20年に一度繰り返す式年遷宮のシステムは、私達の生命を紡いで行く為の重要な文化である。 -

御神楽 三【外宮】
平成25年10月6日
御神楽 三【外宮】
平成25年10月6日遷御の儀から一夜明けた午後7時、外宮では雅楽などを奉納する御神楽(みかぐら)が営まれた。天皇陛下から遣わされた勅使や、臨時祭主の黒田清子(さやこ)さんも参列され、遷御が無事終わったことをお祝いした。浄闇の境内、松明の火だけが御神楽に参列する神職達の足下を照らしている。
-

神嘗祭 御ト参進太鼓【内宮】
平成25年10月15日
神嘗祭 御ト参進太鼓【内宮】
平成25年10月15日晩秋の夕べ、神嘗祭にお仕えする神職達の参進を知らせる太鼓が鳴り響く。清めの雨に庭燎がにじみ幻想的な雰囲気を醸し出している。御トとは、祭典に奉仕する神職が、神の御心に叶うかどうかをお伺いする儀式。
-

神嘗祭 御ト参進 一【内宮】
平成25年10月15日
神嘗祭 御ト参進 一【内宮】
平成25年10月15日御トに向う神職達が参進している。雨の中、整然と進む行列に、神々への畏敬の念が表れている。
神宮では、年間1500回もの祭事が行われるが、その中でも最も重儀とされる三つのお祭がある。6月と12月の月次祭(つきなみさい)、そして10月の神嘗祭だ。因に、式年遷宮は「大神嘗祭」とも言われている。 -

神嘗祭 奉幣【外宮】
平成25年10月16日
神嘗祭 奉幣【外宮】
平成25年10月16日外宮の御祭神である豊受大御神(トヨウケノオオミカミ)に、天皇陛下のお使いである勅使が参向され、幣帛(へいはく)が奉献される。幣帛とは、五色の絹や数種の織物のことで、貨幣の無かった時代、最も貴重なものとして絹織物をお供えしていた伝統を受け継いでいる。
-

神嘗祭 由貴夕大御饌 二【内宮】
平成25年10月16日

神嘗祭 由貴夕大御饌 二【内宮】
平成25年10月16日
午後10時前、神楽殿近くの忌火屋殿(いみびやでん)前に辛櫃に納められた神饌が並べられた。神饌はお祓いをされた後、御正宮をはじめ神苑内の別宮にそれぞれ運ばれる。神嘗祭の由貴大御饌(ゆきのおおみけ)では、その年の新穀を始め、のしアワビや伊勢エビなど約30品目の御馳走が御神前に供えられる。神々の恵み、自然の恩恵への感謝と共に、皇室のご繁栄と国家の安泰、五穀の豊穣、国民の平和をお祈りするのだ。神職や神領地に住む人々は、神嘗祭まで新米を口にしないとも言われており、ここにも日本古来の精神性が表れている。
